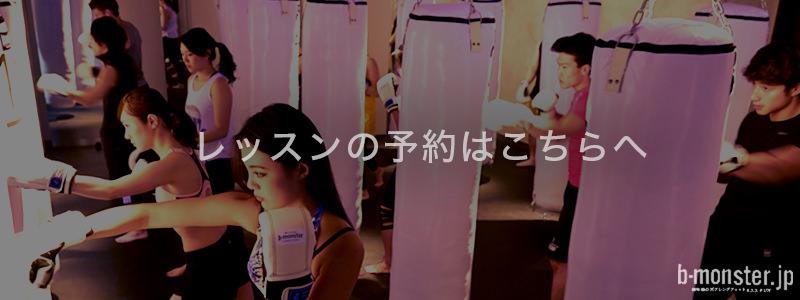b-monsterパフォーマーの横顔"LINQ"「限界突破すれば新しい自分が見えてくる」

豊かな表現力と独創性あふれるプログラムで人気のパフォーマーLINQ。スタジオ内を駆け回り、動き、踊り、熱く鼓舞する。華やかで明るいイメージの彼女だが、日々苦悩する時期があったとか。普段は語られない彼女の内面とプログラムへの想いを探った。
水泳で鍛え、習い事で表現力を磨いた

出身はロシアです。日本人とロシア人のクォーターで、向こうで生まれ育ち、6歳からは青森県で過ごしました。スポーツは2歳から水泳を。種目は自由形の長距離です。中学時代から専属コーチに就いてもらい励みました。中・高・大とインターハイやジュニアオリンピック、日本選手権などに出場したこともあります。
一方で幼い頃からいくつも習い事に取り組み、表現力を磨きました。中でもピアノが好きで曲の背景を読み取り、世界観ごと演奏するのが得意でしたね。その後もエンタメ精神旺盛で、学生時代はDJをしたり、某夢の国のアトラクションキャストをしたり。今もフロントでアナウンスをする時は、キャストの血が騒ぎます(笑)。
運動経験を仕事に生かしたかった

体育大学、大学院のスポーツ科と進み、ゆくゆくは教員にと考えていたんですが、運動経験を仕事に生かしたいと思うようになりました。そこで応募したのがb-monsterです。パフォーマーはスポーツの仕事でありながら、エンタメ的に魅せる要素も十分にある。自分には申し分のない職場だったんです。
研修時代はすごく充実していました。何より同期に恵まれたんです。NIKA、KyoTa、KAREN、SMINE。私はじつはすごい人見知りなんです。でも気づいたら、みんなと打ち解けて、プライベートでもご飯にも一緒に行くようになって。練習はキツかったんですけど、本当に明るく毎日を送れました。
「じつは悩んでいたんです」

デビューは昨年、2019年6月24日、青山スタジオの所属です。1年が経ちますが、ここまでで転機といえば9月です。先輩パフォーマーが一度に数人退職し、自分ももっと頑張らなきゃって意識になった頃です。
じつは当時、悩んでいたんです。下半身強化が多いサーキットを「床と友達」と称して取り組みやすくしたり、曲に合わせ声のトーンを変えて盛り上げたり。そんな工夫が奏功してプログラムは嬉しいことに盛況でした。でも継続して来てくださるメンバー様ばかりかというと、じつはそうでもなくて。大体「ユニークだ」「面白い」で終わってしまう。どこか変わり者に見られるというか、パフォーマーとして認めてもらえていない気がしたんです。何か変えようと思うけど、どこをどうしていいかわからない。毎日、辛くなっちゃって。その時、力をくれたのが二人の先輩です。
二人の先輩が自分を変えた

一人は当時、新宿スタジオで一番人気だった先輩。悩みを相談したところ、先輩も同じように苦しんだことを話してくれました。新宿に異動した直後、人気者ばかりの先輩たちの影に隠れ、やはり継続して来てくださるメンバー様を集めらなかったらしくて。でも熱いハートを持ち続けていれば、いつか報われると信じていたというんです。そして言われました。今、必要なのは自分を信じる強い心だって。もう号泣しちゃって。
もう一人は青山の先輩。HARDも担当していたんですけど受けたら、そのパワフルさにびっくりしちゃって。最高にキツいプログラムなのにキューイングしながら、延々と一緒に動いてくれるんです。しかも常に声をかけて励ましてくれる。だから辛いHARDが楽しい。目を丸くしてたら先輩はHARDは動いて当然だよってさらっと言って。それがまたカッコよくて。自分は動きが足りなかったんじゃないか、力強さが足りなかったんじゃないかと思えてきました。それで自分も思いきり一緒に動いて、メンバー様と楽しめる、そんなパフォーマンスをしたいと思うようになったんです。
その後、vol.1をリニューアルし、思い切り動くスタイルに。と同時にウエアもそれまでTシャツ姿だったのをブラトップに変えました。自分の強さをもっと打ち出そうって。すると継続的にきてくださるメンバー様が増えていきました。また嬉しいことに聞こえてくる声も「面白い」から「かっこいい」に。お世辞かもしれませんけど(笑)。そこからです。自分がパフォーマーとしてスタート地点に立てた気がしたのは。
楽しく鍛え、達成感を得るプログラム

今、私がレギュラーで担当しているプログラムはvol.1と、つい最近リリースしたばかりのvol.2です。
vol.1はサーキットパートはランジ、ジャンピング・ランジなど、下半身強化がメイン。音楽に合わせ、心拍数を一気に上げていきます。強度は少し高めです。パンチパートでは動きだけでなく、ジャンプやステップを存分に織り交ぜ、テンポよくパンチを打ち込めるようにしています。曲を意識しながら、身体中で楽しんでみてください。
vol.2は「根気強さ」と「達成感」をコンセプトに作りました。サーキットは曲ごとに「下半身」「腹筋」「上半身」と部位別に鍛える動きを入れ、パンチパートは手数のあるコンビネーションも多く入れています。強度は控えめながら、ひとつ一つの尺が長くジワジワ効くようにしています。最後まで集中力を途切れさせず、終わった後のスッキリした気分を味わって下さい。
自分は「動くパワースポット」

プログラム前には「ジャンピングタイム」があります。これは水泳や陸上の選手がレース前に行うジャンプを取り入れたウォーミングアップです。その際、先輩パフォーマーMARIさんのvol.3の曲を流すんですけど、それは大学院で何曲か流して脳波を調べてみたら、それが私のvol.1と一番波長が合ったので。気持ちを高め、スタートと同時にフルスロットルで動いていただければ。
終了後は「リラックスタイム」といって、音と照明をすべてオフにし、リセットする時間を設けています。これは興奮状態を一気に鎮めるため。血液の循環が改善し、疲労回復効果を高めます。ジャンピングタイム、リラックスタイムともに大学院時代の友人に協力してもらい考えましたが、じつはちゃんと裏付けがあるんですよ。
プログラムで意識していることは、先に言った通り、メンバー様と一緒にめちゃくちゃ動くこと。あとは一人として置いてきぼりにしないこと。やはりいらしていただく以上、全員に満足していただきたいんです。迷子になっている方はいないか、正しく動けていない方はいないか、とにかくよく見ます。気になったらすぐそばにいって動いたり、煽ったりしますね。
プログラムのラストでは「イヤなことがあれば出しきって」と言っています。皆さん、ただ体を鍛えたいだけじゃなく、ストレスを解消したい方も多いと思うんです。なのでここで思い切りぶつけてもらえたらなって。私は自分を「動くパワースポット」だと思っているんです。私を見ていただけたら大丈夫、一緒に動けば元気になるからって。そんな風に応援する気持ちでやっています。最近はありがたいことに、私のプログラムはラストが楽しいと言っていただいたり、涙してくれる方までいたり。本当に嬉しいですね。
「刈り上げ」は個性の象徴

趣味は読書とスケボーです。本は何でも読みますけど、中でも松岡修造さんのような熱いハートを持つ方の本が好きです。スケボーは10歳から滑っていて、どこへでも行っちゃいます。あとは釣り。青森の実家が海のそばだったので昔から好きで、今も機会があればするし、釣り堀にもよく行きます。それから料理ですね。魚料理などの和食を中心にケーキなんかも作ります。意外と家庭的なんですよ!
髪型? 刈り上げですか(笑)? これはファッション系の仕事をしている母の影響で変わった髪型にしたかったのと、人とかぶりたくないのでやっています。あと髪を下ろしていると普通の女性なんだけど、結んだら強そうに見える。たまに怖がられますけど(笑)、そんな風にイメージを変えられるのも面白いなって。もう4年くらいやっていますね。
b-monsterの魅力は、パフォーマーそれぞれに個性があって、プログラムが多彩なことですね。しかも同じプログラムでも、受けるサンドバッグによって印象がまるで違う。私はプログラムって、ある意味、パフォーマーによるアトラクションやショーのようなものだと思っているんですけど、それだけ存分に楽しみながら、ボディメイクできるフィットネスは他にないと思いますよ。
一番やりたいのはHARD

私のvol.1プログラムのコンセプトでもあるんですけど、メンバー様には「限界突破」を心がけていただきたいです。限界突破すると新しい自分が見えてきます。私も水泳をやってる頃、ラストは決まって100mを100本泳ぐんですけど、それって本当にきついし、身体もふらふらになる。でもやり通したことで身体もメンタルも強くなりました。いや、そんな大げさに考えなくてもいいです。プッシュアップの回数を上乗せするでも、いつもよりイエー!の声を大きくするでも何でもいいんです。絶対に楽しいはずですから。自分を追い込むことで、新しい自分を発見してみてください。
今後は新しいプログラムをもっと出したいし、イベントも担当したいです。でも一番やりたいのはHARDです。もともとキツいのが好きな性格なのと、先輩のHARDを誰よりもたくさん受けた自負があるので受け継ぎたい気持ちがあって。そして何より最も大変なプログラムだからこそチャレンジしたいです。自分もこれまで以上に限界突破して、メンバー様と一緒に成長したいと思うんですよね。

音楽制作会社、カルチャー誌での勤務を経て、フリーランスの編集者・ライターに転職。現在は雑誌やウェブサイトなどで、音楽をはじめエンタメ、スポーツ、飲食などの記事を執筆。b-monsterは、約2年にわたって週3~4日ほど通っている。
photo by Jun Yamashita